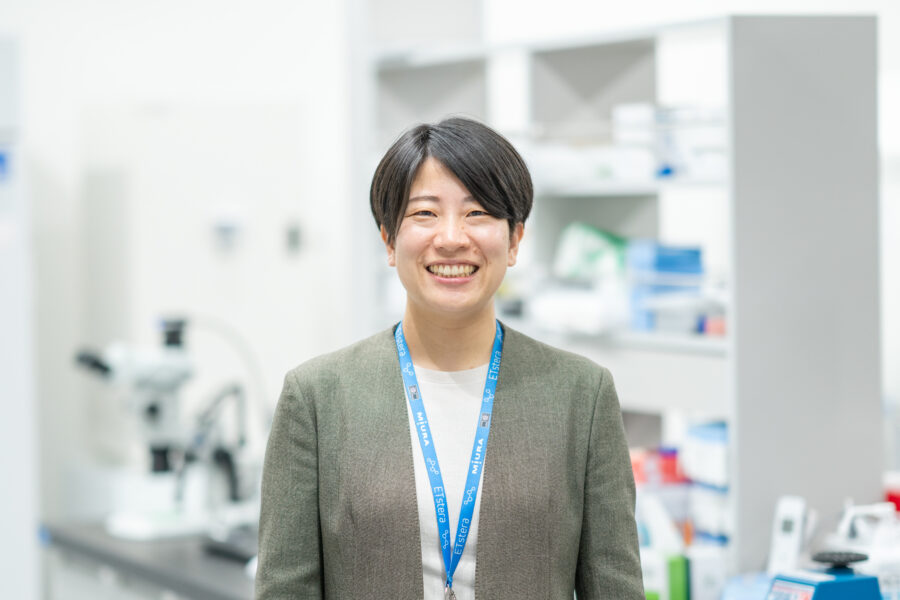「本当は駄目なんだけど」の「本当」はいつ来るんだろう
-福島さんが看護師の道に進んだ経緯を教えてください。
母親が看護師だったからというのもありますが、あまり成績のいい学生ではなかったので(笑)、資格を持っていれば食いっぱぐれることはないだろうと思い、選んだのが看護師の道でした。入試の時にはかなり苦労しましたが、奇跡的に国家試験に合格し、面接試験のみだった病院に採用してもらうことができました。
最初に就職したのは、鹿児島県の中では比較的規模の大きい総合病院で、年間4000件ほど手術を請け負うオペ室の看護師として働きはじめました。オペで使い終わった器材の洗浄・滅菌は僕らが担当し、ローンインスツルメントの再生処理だけ下の階にあった中材にお願いするような運用でした。


-当時の病院の再生処理の実施状況はいかがでしたか?
当時の僕には洗浄・滅菌についての知識があったわけではなかったですし、病院内に再生処理の勉強している人がいたわけではなかったんですが、それでも日々の運用の中で引っかかることがたくさんありましたね。
たとえば、当時は単回使用医療機器(SUD)を再滅菌して使用するのがあたりまえのような状況で、周りの看護師からは「本当は駄目なんだけどね」と言われていたんですが、その「本当」はいつ来るんだろうと、ずっと疑問を持っていたんです。さきほどお話ししたように勉強は苦手だったものの(笑)、知識欲はとにかくあったので、疑問を解消するために、研究会にいくようになったんです。当時熊本と鹿児島で年1回開催されていた滅菌業務研究会にはかならず参加していましたし、お金と時間に余裕があれば医療機器学会にも参加するようにしていました。

はじめて県外の研究会に参加した時、こんな世界があるんだなと、本当に視野が広がる思いがしたんですね。普段の生活では絶対に出会えないような、桁違いの知識量の人たちがたくさんいて、これは褒め言葉ですけど、変態だとしか思えないくらいなんですよ(笑)。そういった人には惹きつけられましたし、いまのままではダメだな、僕もこういう人になりたいなという衝動に駆られたんです。

悩みを打ち明け合う、カフェスタイルの「考える会」
-第一種滅菌技師の資格を取得されたのはいつでしたか?
最初に就職した病院で5年働いたのちに、結婚して子どもができたタイミングで少し規模の小さい医療センターに転職したんですが、前職より手術件数が少なく、少し時間に余裕ができたため、再生処理について本格的に勉強しようと、第一種滅菌技師の資格を取得しました。

当初は自分に資格が取れるかどうか不安だったんですが、2009年に仲の良い先輩と鹿児島滅菌業務研究会に参加した際に、鹿児島市立病院の方が鹿児島初の第一種滅菌技師取得者として発表されていたのを見て、めちゃくちゃかっこいいなと思ったんですね。当時は資格についての情報が入手しづらい時代だったので、まずはその人と仲良くなろうと(笑)。先輩と一緒にお近づきになり、2011年には無事に僕らも資格を取得することができました。その後、2016年に「鹿児島滅菌供給を考える会(以下、考える会)」を一緒に立ち上げたのもその3人でした。


-そうだったんですね。「考える会」を立ち上げようと思ったきっかけはどのようなものでしたか?
以前から開催されていた鹿児島滅菌業務研究会は、県内の主要な病院の師長が集まる場なんですが、大きな病院では異動してきたばかりの方が師長を務める場合も多いため、再生処理の知識があまりない方が中心となって運営されている現状があります。なので、現場経験があり、資格取得者でもある僕らに研究会を設立してほしいと、当時の会長から打診をもらったのがきっかけでした。

同時に、当時の鹿児島では滅菌技師資格の更新に必要な単位を取得できる場が鹿児島滅菌業務研究会しかなく、年に1回しか開催されていなかったので、毎年参加したとしても単位が足りない状況があったんです。鹿児島には離島もありますし、更新のために県外の研究会に参加する必要がある状況だと、資格取得者は増えていかないので、僕らが単位を発行できる研究会をつくろうと思ったんです。

-どのような意識で会を運営されていますか?
僕としては、再生処理の業務があまりにも見過ごされている状況を見てきたので、きちんと世の中から認められる仕事にしたいという気持ちがあったんですね。リソースがまったく異なる中でも、ガイドラインに書かれた滅菌保証の水準を達成することは、どの規模の病院にも求められるわけですよね。大規模の病院と同じことができないからといって諦めてしまうのではなく、最適解を考えることはできるんじゃないかと思うんです。研究会を立ち上げた背景には、そういったことを話し合えたりする場をつくりたかったからでもあります。小さい病院にはその規模なりのベストがきっとあるはずで、最適解を見つけられるきっかけを少しでもつくりたいなと。

また、普段僕が学会などの場で発表する際に、質疑応答の時間より、終わってから声をかけてくれる方との会話の方が大事なことが多いんですね。だったら最初からそんな場をつくりたいなと思い、僕らの会では飲み物や食べ物をかならず用意をして、日々の仕事の中で気になっていることを自由に話してもらえるような、カフェスタイルでやりたいと思っているんです。できるだけ敷居を下げて、話しやすい場所にしたいと思うので、講演していただくメーカーの方にも、なるべくネクタイはしないでくださいとお願いしています。
「考える会」という名前はついているんですが、どちらかというと悩み相談所のような場所を僕らはやりたいと思っています。最近は参加してくださった方から、「私も第一種滅菌技師を取りました」「あの設備を導入することができました」といった報告をしていただくことが増えてきましたね。

正論を振りかざさず、妥協点を見つけていくアプローチ
-福島さんが再生処理の仕事にやりがいを感じるのはどんな時ですか?
もちろん、オペ室の看護師として働いてきた中で、術後感染症のリスクを極力ゼロにしたいという思いで一生懸命やってきましたが、単純に器材がピカピカになっていくのを見るのが気持ちいいんですよね。こう言うと気持ち悪がられるかもしれないですけど(笑)。ぼーっとしたあたまで朝出勤してきても、ちゃんとオートクレーブが動いているのを見るだけで嬉しくなったり、オートクレーブのカウンターがゾロ目になるのを楽しみにしたりしています。いまは現場を離れていますけど、再生処理の仕事は本当に好きですね。

-これまで勤務されてきた病院では、再生処理の質の向上のためにどのようなことに取り組まれてきましたか?
総合病院の次に就職した医療センターでも、先ほどお話ししたようなSUDの再利用がおこなわれている状況があり、当時の実状を学会で発表し、再利用を中止に持っていくことをしたんですね。当時はかなりスキャンダルでしたし、もちろん発表する前にセンター内の審査で引っかかったんですが、SUDを再利用するリスクと、通常の器材をきちんと再生処理した場合のコストの違いを示すことで、最終的には発表にまで持っていくことができました。当時、県内の病院でそこまで踏み込んで再生処理に取り組んでいる病院はなかったので、かなりの反響がありました。はじめての学会発表でしたが、張り切って取り組んでよかったかなと、いま振り返っても思います。

-最終的にセンターが発表の許可を出したのも画期的ですね。
発表までの過程はもう喧嘩の連続でしたよ(笑)。結果的に病院内の仕組みを大きく変えることができ、SUDとリユースできる器材を並行して利用することで、コスト削減にもつながりました。最初に就職した病院ではなにもできなかったことがずっと引っかかっていたので、とにかく必死でしたね。当時はまだ20代で、師長さんからすれば相当面倒な存在だったと思います。

ただ、病院の仕組みを変えられたことはもちろんよかったんですけど、自分の主張を絶対に曲げない姿勢でいたことで、結果的に傷つけてしまった人がたくさんいて、そのことに自分自身も傷ついていたと思うんです。結果、第一種滅菌技師の資格を取った頃に燃え尽き症候群になってしまい、一度休職することになりました。やっぱり、頑張りすぎはよくないと思います。
復職にあたって環境を変え、それまでの学びを活かすためにも、正論を振りかざすのではなく、相手の意見や主張を聞きつつ、妥協点を見つけていくアプローチに変えていきました。いま思うと当時は本当に青かったなと思います。自分が師長の立場になり、若手の看護師と接していると尚更感じますね。

いま悩んでいることは次の世代のための地盤になる
-研究会に限らず、再生処理の情報発信の際に意識していることはありますか?
僕は感染制御実践看護師の資格も取得しているんですが、日本看護協会が掲げている10項目の標準予防策のひとつに再生処理の項目が入っているものの、看護師の中でも意識的に取り組んでいる方の数は少ないですし、苦手意識が強い方も多いので、感染管理の立場からその意識を変えていけるような発信を今後していきたいと思っています。
看護師の方は、学校のカリキュラムの中で再生処理について少し学びますが、現場経験を積まない場合も多いので、どうしても中材の業務に敷居の高さを感じてしまっている状況があると思うんですね。再生処理は片手間にやるような仕事ではないと思うので、できれば看護師は看護に専念できる状態が理想だと考えていますが、規模やリソースによっては兼任しなければならないと思うので、お互いリスペクトし合えるような状況をつくっていきたいと思っています。

また、中材は医師を説得しないと変えられない状況がありますし、どうしても病院の管理職の方々の意識が変わらないと現場も変わっていかないので、最近は僕らの研究会に参加してくれるような現場の方向けの発信に加えて、医師や師長さんといった管理職向けにも発信するようにしています。ここ数年、鹿児島滅菌業務研究会から依頼を受けて僕が講師として登壇することも増えているので、そういった方々の前で話すことの意義を感じています。

-最後に、今後の研究会の運営を通して取り組んでいきたいことをお聞かせください。
今年で僕は48歳になるんですが、60歳まで働くとしても、「あと12年もある」と考えるようになったんです。中材で必死に働いている人は、できることなら明日にでもこの状況を変えたいと思っているはずなんですが、僕自身が焦っていた時期を経験したので、いま悩んでいることは次の世代のための地盤になるはずで、決して無駄にはならないんだと伝えていきたいですね。すぐに100点にはできないかもしれないけれど、次のステップに進むことはできるはずですし、首都圏の病院と競る必要はなくて、鹿児島だからこそやれることはあるはず。
それに、中材で働く方々には、ひとりで悩むのではなく、ぜひ研究会で仲間をつくってほしいですね。同じ目標を共有できる人と出会うことができれば、少しでも前向きに取り組んでいけるんじゃないかなと。僕らはなにかを教える立場ではないので、一緒に模索していける存在でありたいと思っています。

また、この世界はどんどんスタンダードが変わっていきますし、もちろんこれからも勉強し続けるつもりなんですが、それよりも人を育てることが第一だと思っています。引き際をちゃんと見極めて、「老害」にはなりたくないんですよね(笑)。現場の人はもちろん、研究会のような場で講演ができる人や、研究会の運営をお願いできる人を育てて、ちゃんとバトンを渡すことをこれからの目標にしていきたいと思っています。僕にとって研究会は大事な場所ですし、みんなにとっても必要な場所であって欲しいって思うからこそ、私物化だけはしたくないんです。現在、研究会にはオンラインを含めて毎回100名くらいの方が集まっていますが、このくらいの規模がちょうどいいと思うので、参加したみんなが情報を共有できる場として継続していければと思っています。

※ご所属・肩書・役職等は全て掲載当時のものです。