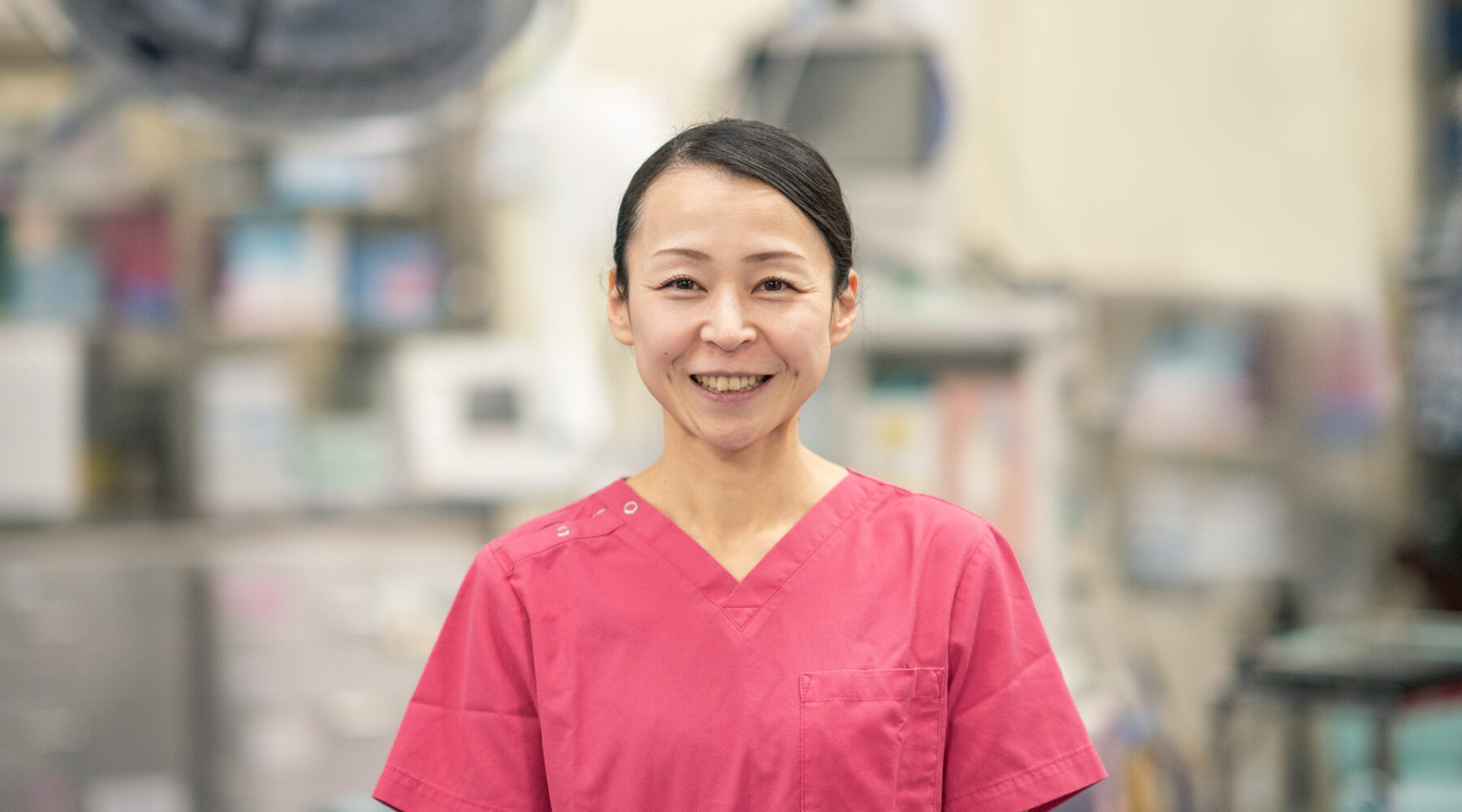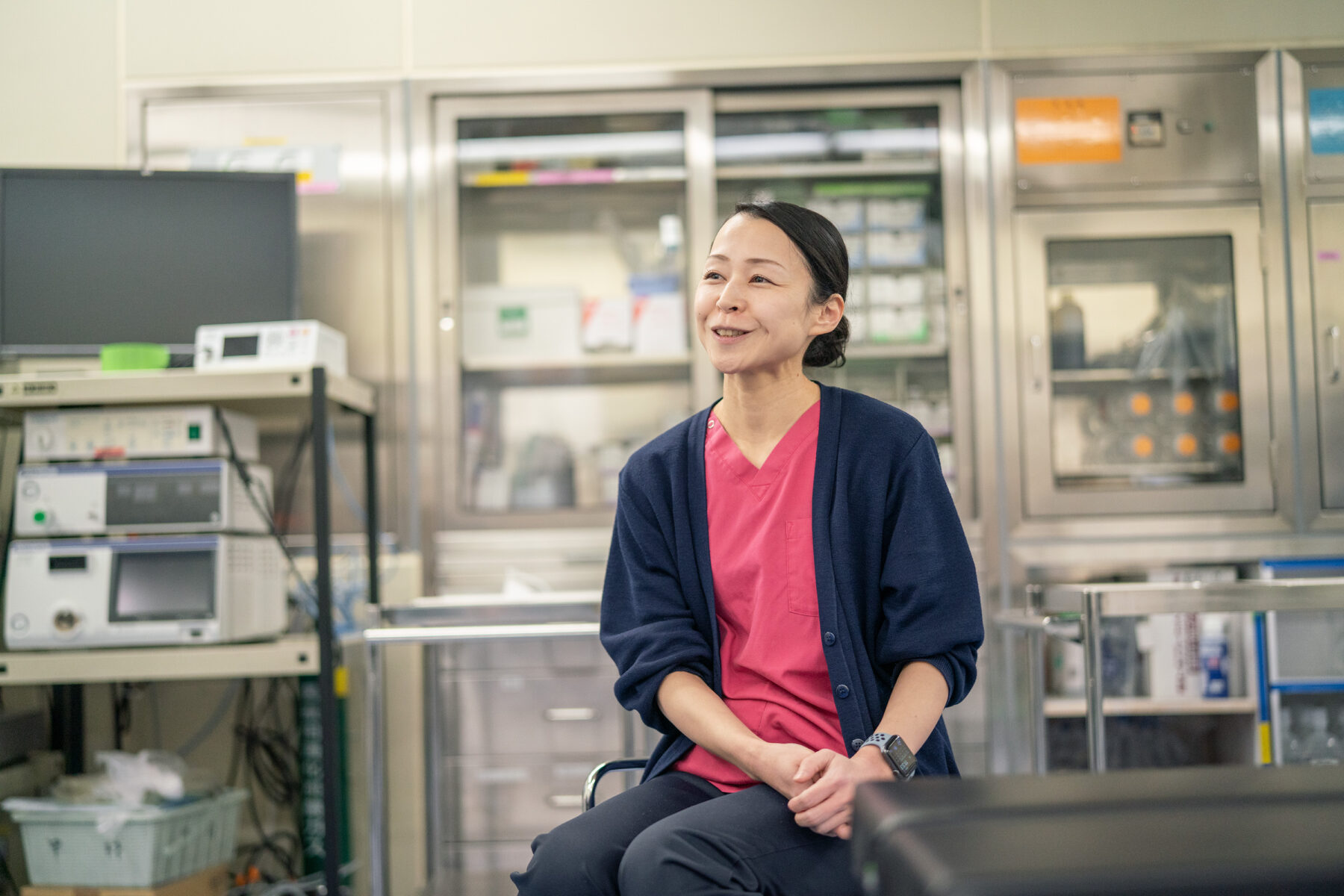
「私たちのような病院の現状こそ、学会で発表するべきでは」
-西島さんが看護師を目指したきっかけを教えてください。
もともと看護師という仕事に強い憧れがあったわけではないのですが、母が看護師だったということもあり、高校の進路選択の際に、自然と看護の道に進むことを決めていました。親としてはできればこの道を選んでほしくなかったようで、当時は大反対されていたんですが、受験票を出すギリギリまでどこを受けるかは黙っていて(笑)、「もう決めたから」とそのまま受験をして短期大学に進学しました。
卒業後は、大学の附属病院に就職することになり、さっそく手術室に配属されることになりました。当時の私にとって看護師といえば病棟で白衣を着て仕事をしているイメージしかなかったので、正直なところ、手術室に配属になった時には戸惑いもありましたね。

-再生処理の仕事を経験されたのはその頃でしょうか?
手術が少ない夜間や土日に、洗浄が終わった器材のセット組みや包装などを手伝うことはありましたが、大きな病院だったので、手術室の中に独立した中材があり、再生処理は専任スタッフが担当していました。なので、基本的に手術室の看護師は手術に専念して、洗浄器や滅菌器を動かすことはなかったですね。中材部門の方々と直接関わることも少なかったですが、器材を使う側である手術室から、処理する側である中材の人たちへの配慮を学んだように思います。
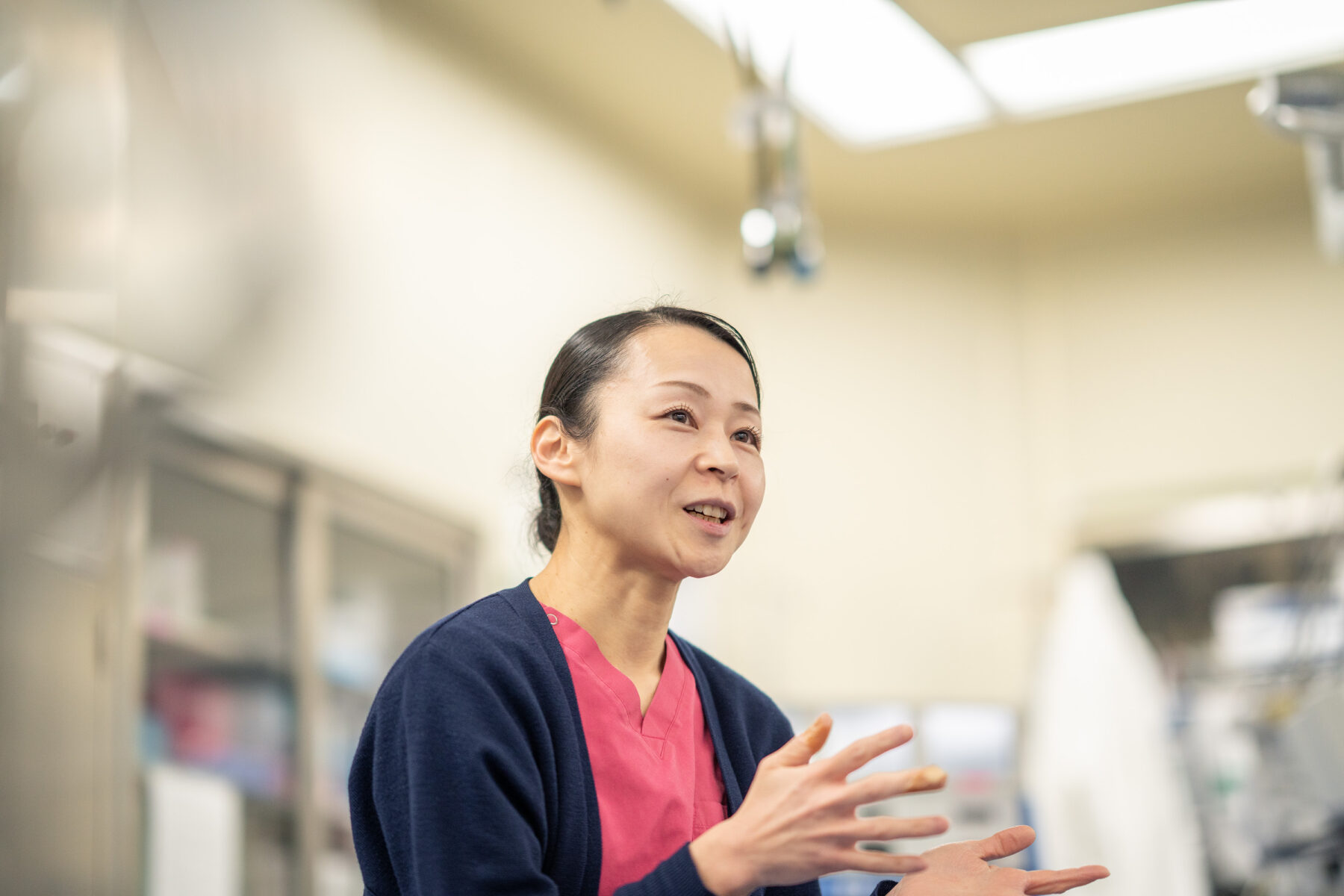
-その後、再生処理について学ぶようになったのはいつからですか?
大学病院を9年務めたのちに、小さい病院へと移ることになり、そこで手術室と中材の責任者として、はじめてきちんと再生処理に関わることになりました。当時は前任のやり方をそのまま教わっていただけで、機械のスイッチを押してさえいれば洗浄も滅菌も問題なくできていると思っているような状態でした。
その後、内視鏡の業務に携わるようになり、勉強会に通うようになったのですが、そこでは内視鏡の洗浄方法について学ぶ講義が一コマ分あったんですね。その時、いかに機械洗浄の前の用手洗浄が大事なのかをはじめて知り、洗浄器に頼りすぎている当時の運用に疑問を持つようになりました。


それからは、セミナーや講習会、学会、カンファレンスなどの場に足を運ぶようになり、ほかの病院ではどのようにやっているのかを徐々に学んでいきました。ところが、学会に参加していくうちに、そこで発表されているのは大きな病院の方々ばかりで、小さい規模の病院が太刀打ちできるような内容ではないことに、悶々とするようになっていたんです。小規模で働く看護師のなかには、学会発表を聞いて諦めてしまう方もいるでしょうし、むしろ私たちのような病院の現状こそ、学会のような場所で発表するべきなのではないかと。いま思えばかなり大それた野望を抱いていたと思います(笑)。

中材業務の効率化は、手術室からはじまっている
-当時の病院では、まずはどのように改善していったのでしょうか?
セミナーなどに参加して得た知識をなんとか現場に活かす方法を考えていました。とはいえ機械の購入などは難しかったので、まずは中材内の動線を整えることからはじめていきました。その病院では、使用済みの器材を中材に持ち込む窓口はあったんですが、あまり運用のルールが守られておらず、清潔エリアを通過して運ばれることもありました。なので、まずは器材を受け取る場所と払い出す場所を分ける動線を守ることに協力してもらいました。小さい病院の場合、大きい病院のように明確にゾーニングすることは難しいですし、まずはルールをきちんと守ってもらうことで、動線を確保していったんです。

-その後、東京北部病院に移られた理由は何だったんですか?
手術室の看護師として、もっと外傷手術の現場を経験したいと思ったのが理由です。当時の病院ではじめて外傷手術を経験し、興味を持ったんですね。東京北部病院は救急車を受け入れているため外傷手術の件数が多く、転職を決めました。
外傷手術には他の手術にはないやりがいや、独特の勢いがあると思っています。骨折の仕方は年齢や体型によって個人差があるため、毎回どうやって治すのか考えながら手術の準備をするおもしろさがありますね。

-そういった外傷手術が多いからこその、再生処理の業務の特徴はありますか?
外傷手術の場合、借用器材を用意する必要があるため、器材の数が十分ではない時のやりくりが難しいと思います。少ない数の器材を正しく安全に運用していくには、先生の協力が必要ですし、足りなくなりそうな器材があれば、事前に先生と打ち合わせをすることもあります。
私がここに来る以前は、実際には使わない器材を手術時に用意していたり、足りなくなった分をフラッシュ滅菌していたりするような運用でした。フラッシュ滅菌に頼った運用は危険ですし、器材の不足はスタッフの焦りや作業時の見落としにもつながります。現在は、同じ種類の手術が続く場合は先生に使用器材の代案を出してもらったり、手術中に使用する器材を調整していただいたりしています。フラッシュ滅菌のような抜け道を見つけるのではなく、正しい方法と対策を考える運用に変えることで、器材の数でオペの件数が制限されてしまうようなことはなくなりました。
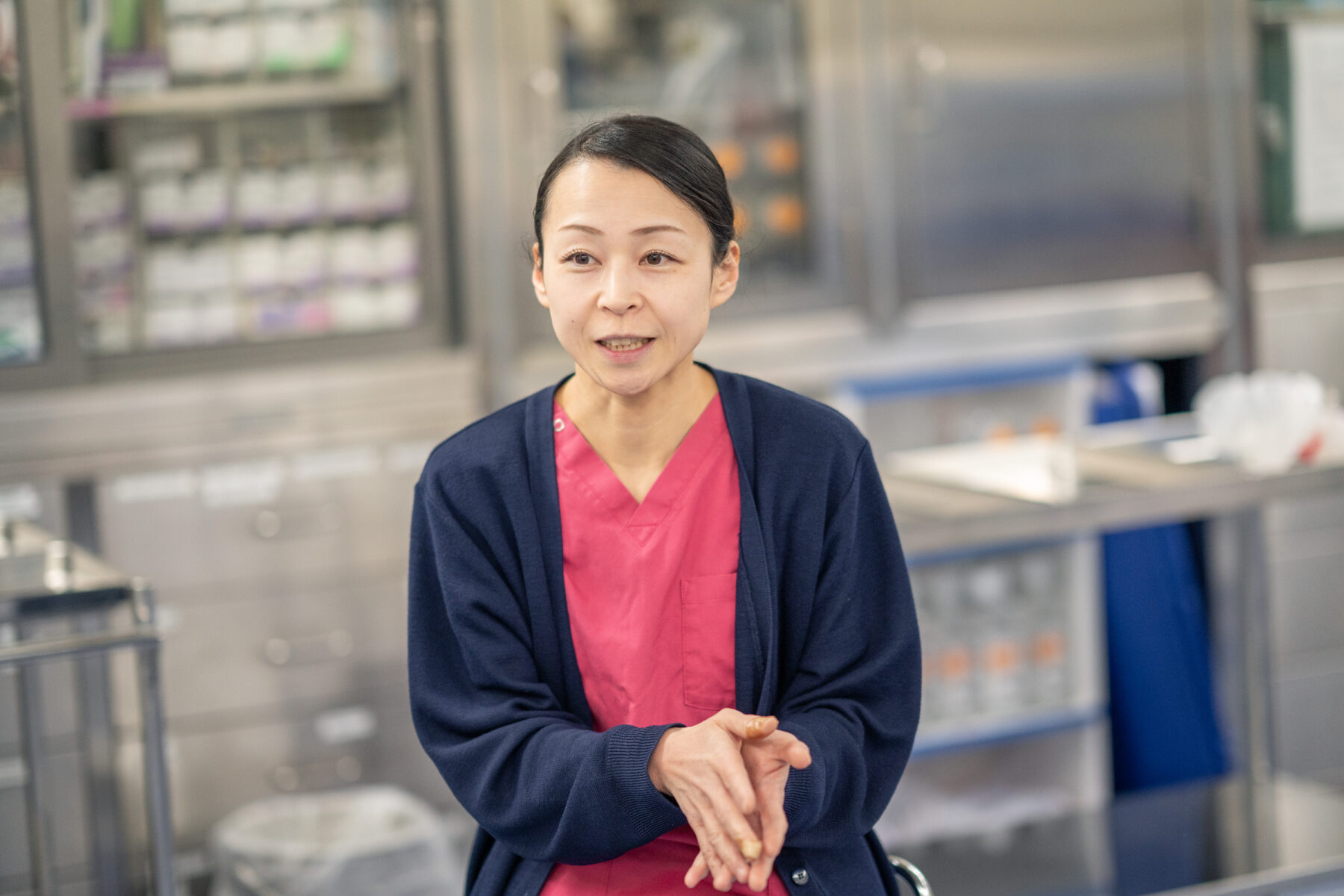
とはいえ、フラッシュ滅菌をなくすまでには、かなり先生との議論が続きましたね。「事務員に滅菌器のボタンを押させれば十分」と思っている経営者は実際に存在しますし、滅菌作業においていままでのやり方や習慣が幅をきかせている病院も多いと思いますが、滅菌はもはや確立された学問です。小さな病院であっても、スタッフがエビデンスを理解し、ガイドラインを遵守しなくてはなりません。

-それだけ医師の方々とのコミュニケーションを重ねることができる環境は、この規模の病院ならではのことでしょうか?
そうですね。先生の考え方にもよりますが、小さい病院だからできることだと思います。目の届く範囲に仲間がいますし、変更事項があった時にはすぐに伝えることができ、わからないことがあったらすぐに聞いてくれるので。
とはいえこれまでに何度も失敗してきましたし、いまでも「こうすればよかったな」と思うことばかりですが、繰り返し取り組むことで、病院の中のスタンダードをつくることができてきたと思います。最近は私が忙しくて目が行き届かない時でも、なにかあった時にスタッフ同士で気がつくことができるようになっていますね。

-西島さんが考える、中材の仕事のおもしろさは何だと思いますか?
洗浄・滅菌の正しい知識を身につけること自体におもしろさはあるんですが、いかに質を維持しながら負担を少なく業務をおこなうのかに興味があり、知識をベースにいかに効率よく正しい運用をしていくのかを考えるのが楽しいですね。私は中材の業務の効率化は手術室からはじまっていると思うので、中材だけを切り出して考えるのではなく、お互いの仕事に配慮し合いながら、使いやすく、スピーディーな運用を実現するための工夫が必要だと思います。

小さな病院が「やってみよう」と思える学会発表
-西島さんには2024年にSALWAYが共催した日本医療機器学会のランチョンセミナーにご参加いただき、そこでの酒井先生(本シリーズvol.3にて登場)の発表がきっかけとなり、10月に開催された第28回病院サプライカンファレンスにて「小規模病院でもやってみた!〜データロガーを使わないバリデーション〜」を発表されました。反響はいかがでしたか?
SALWAYさんが共催されていたランチョンセミナーに参加した際に、酒井先生がデータロガーを使用しないバリデーションの方法についてお話しされていて、うちの病院でもできそうだなと思ったんですね。うちのような小さな病院の場合、お金も時間もないなかでちゃんとしたバリデーションを実施するのは無理だと思っていたんですが、滅菌器の温度をデータロガーで記録するのではなく、BIを使用して菌が死滅しているかどうかを確認することで滅菌の質を担保する方法があるのを知り、実際にうちの病院でやってみたことを、病院サプライカンファレンスにて発表させていただきました。

再生処理についてなにが正しいのかの知識を身につけることが大事ではありますが、一度知ってしまうと、改善したいのになかなかできないという葛藤を、私たちのような小さな病院の看護師は日々抱えることになります。発表後アンケートでは、「うちでもやってみようと思いました」と回答された方が数十名いらっしゃったようで、そういった葛藤を抱えた方に届けることができ、大成功だったと思っています。
また、次回の日本医療機器学会のランチョンセミナーにて、現在取り組んでいる洗浄のバリデーションについて発表したいと考えています。洗浄器の性能は徐々に落ちていってしまうため、使い続けるためのメンテナンスと検証は必要不可欠です。滅菌の場合、BIやCIがインジケータのスタンダードとして使用されていますが、洗浄のインジケータはまだまだ認知度が低く、導入できていないところも多いと思うんですね。

現在、テストデバイスを使った洗浄評価に取り組んでいるんですが、この方法を確立することができれば、水道代や洗剤の分のコストダウンを図りながら、その分他の設備の購入に予算を回すことができるようになるかもしれません。残念ながら中材はお金を生み出すことができる部署ではないので、年間のランニングコストを見直す運用方法の確立が、予算が少ない小さな病院が踏み出せる改善のための第一歩になるのではないかと考えています。

中材の質を委ねられている、小さな病院の看護師に寄り添う
-西島さんが小さい病院の声を届けたいという使命感を持ち続けてられている理由は何だと思いますか?
日本は大きな病院よりも中小規模の病院の方が数としては多いんですね。患者さんの数は大きい病院を合わせた数の方が多いのかもしれないですが、規模を問わずどの病院でも手術を実施している以上、再生処理に求められる質はどの病院でも同じですよね。
中小規模の病院の多くは、洗浄器と滅菌器さえあれば十分だと考えられていることが多く、再生処理のルールや正しいやり方を知らない病院も少なくありません。それに、機材は持ってるだけでは十分ではなく、使い続ける中で維持していくためには、性能を確認していく必要があります。それを実践できていない病院がまだまだたくさんあることを知ってからは、中小規模の病院で働く人の声こそ届けなくてはいけないと思うようになりました。


欧米の場合、手術を受けられるのは大きな規模の病院に集約されており、法律も整備されていますが、日本にはそういったものはないですし、ちゃんと取り組んでいたとしてもその分保険点数を算定できるわけではないので、中材を担当してる人の知識や技量にすべてが委ねられています。今後は徐々に日本の水準を欧米各国に近づけていく動きがあると思いますが、大きな病院だけですべての患者さんの手術に対応することはできないですし、中小規模の病院が存続していくために、基準を満たすことができる方法を考えていく必要があります。
なので、少しでも中小規模の病院の看護師さんが取り組めることを発信していきたいですし、学会の方々が小さい病院の現場に目を向けるためには、声を上げ続けることが必要だと思います。

-西島さんは、日本医療機器学会が2025年度より事業化を予定している、滅菌供給部門の評価をおこなうサーベイヤーも務められています。最後に、今後サーベイヤーの活動を通して取り組んでいきたいことをお聞かせください。
本格的な事業化は25年4月以降を予定しているため、これまでは準備段階の活動ではありましたが、応募いただいたいくつかの施設にサーベイヤーとして訪問することができました。
私が持つ強みとしては、大小どちらの規模の病院の現状も知っていることだと思いますし、サーベイヤーのメンバーのなかに私のように小さい病院で働く看護師がいるというだけで、同じ状況の方々が受審しやすくなると思うんですね。事業が始まってからも、小さな病院に寄り添うことができるサーベイヤーとして、頑張っている看護師の方々その声を少しでも拾っていきたいと思います。
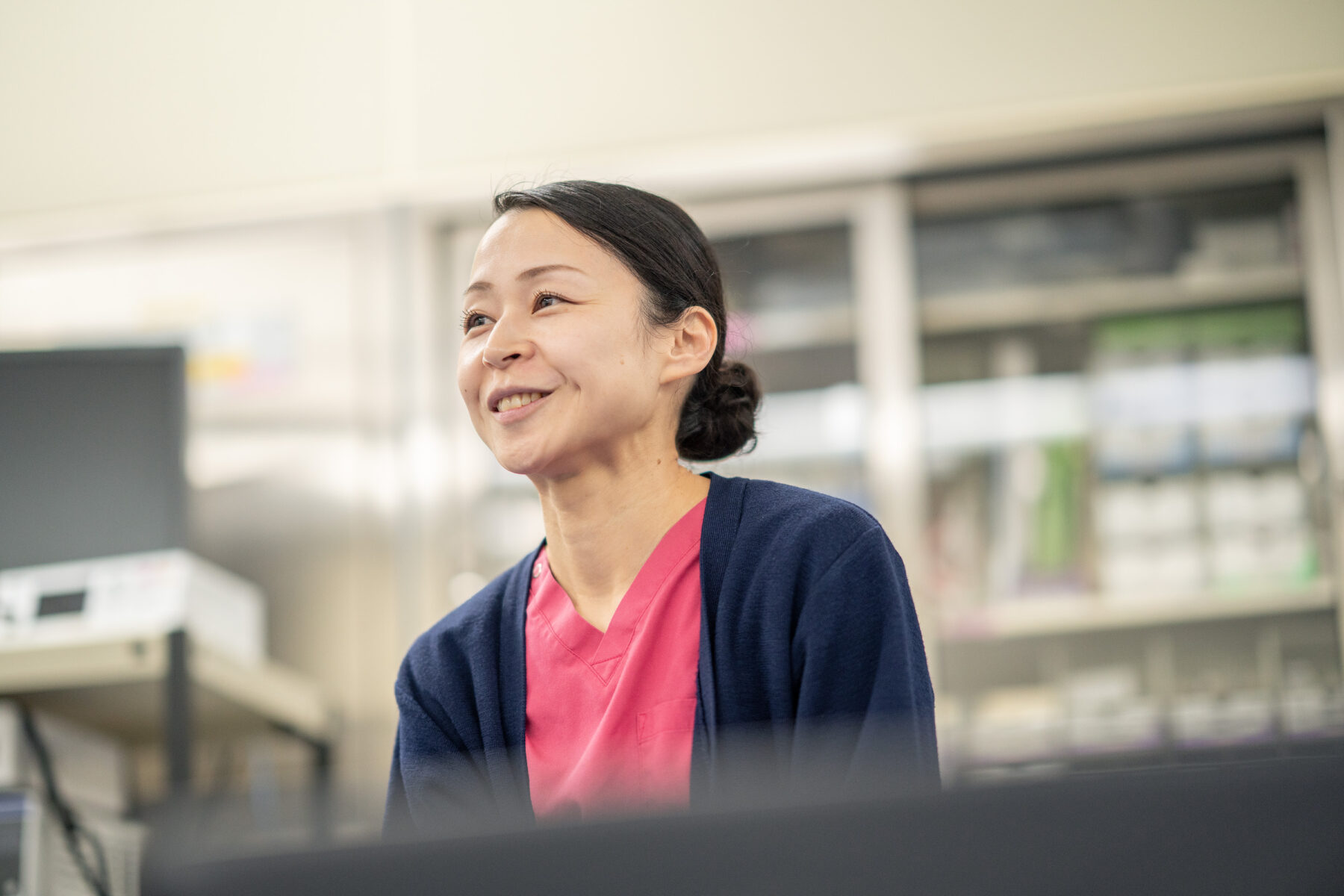
小さい病院の場合、そもそも滅菌技士(師)がいなくて、ガイドラインや評価ツールの存在自体を知らない場合も多いですし、評価ツールに書かれている内容を理解する上でのハードルがまだあるため、なかなか実施されていない現状があります。評価ツールの策定メンバーからすると、実施できていて当然だと考えていた項目もできていない病院も多いので、今後もサーベイヤーの活動を通して、どのように現状の差を埋めていくことができるかを考えていきたいと思います。
※ご所属・肩書・役職等は全て掲載当時のものです。